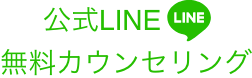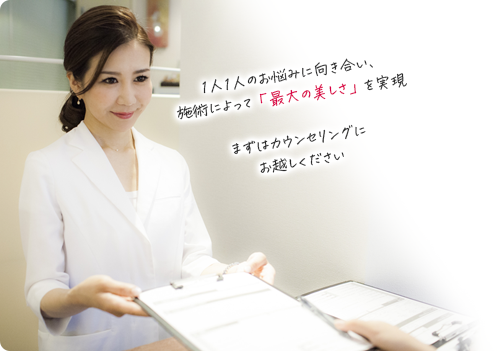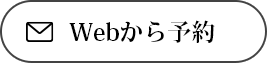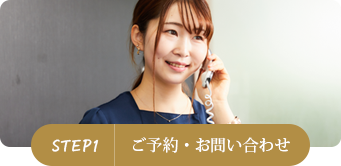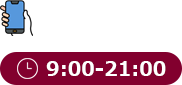「歯科や整形外科でレントゲンを撮る予定があるが、ヒアルロン酸が影響しないか心配」、「写り込んで診断がズレたり、保険適用が難しくならないか不安」、「CTやMRIも含め、画像検査と美容治療をどう両立すべきか知りたい」、など不安な方もいらっしゃるかと思います。
レントゲン撮影前に「ヒアルロン酸、大丈夫?」と不安になるあなたの為に、「いつ・どこに・どれくらい注入している場合に写るのか」「写るならどう対処するか」を徹底解説します。美容施術と医療検査を安心して両立したい方は必読です。
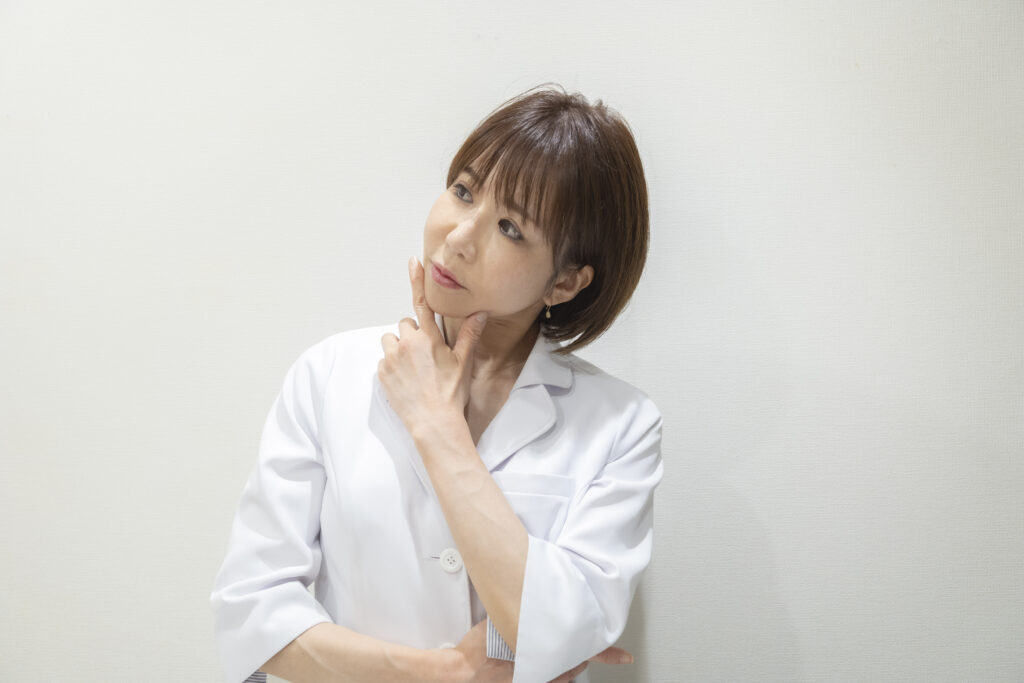
ヒアルロン酸はそもそもレントゲンに写るのか?
1.単純X線(レントゲン)
ほぼ写らない
理由:主成分は水と糖鎖でX線吸収係数が軟部組織と同等の為
2.CT
低濃度であれば不明瞭、架橋度が高い製剤は薄く描出
理由:CTは密度差を階調表示するため、高濃度製剤は灰白色の影として出ることがある
3.MRI
T1強調で中間信号、T2強調で高信号
理由:含水率が高く、脂肪と筋肉の中間に位置づく
4.超音波
高エコー域に不整な反射像
理由:ゲル状物質は音響インピーダンスが皮下脂肪より高い為
● 顔面用の柔らかいヒアルロン酸はX線・CTではほぼ検出不能
● 輪郭形成用の高弾性・高濃度製剤は、CTで薄い影を形成する可能性
● MRIでは体内水分量が多いほど高信号。術歴のメモは必須
写り込むケースは「部位」「量」「時期」の3条件が重なるとき
1.部位:骨膜近く・深層注入
鼻根・顎先・頬骨上の骨膜下に高弾性製剤を3 cc以上注入した症例で報告例あり
2.量:同一部位あたり2 cc以上
充填量が多いとゲルの集積が密度差を生み写りやすい
3.時期:注入後1年以内
代謝が進むとゲルは小分子化→水に近づき透明度上昇

レントゲン診断を妨げる3つのリスク
1.病変の「かぶり」による誤診
副鼻腔炎、顎骨嚢胞など骨近傍の病変とオーバーラップし、境界が曖昧になる可能性。特に頬骨洞CTでは注意。
2.アーチファクトによる画質劣化
高濃度フィラーが一部金属様アーチファクトを生むことがあり、微細骨折の検出率が低下。
3.治療計画の遅延
歯科インプラントや顎矯正手術で、正確な骨量測定が必要な場合に治療日程がズレることがある。
トラブルゼロのための「医療機関共有シート」
1.画像検査予約時
必要情報:①注入日 ②製剤名 ③注入量 ④解剖層
理由:事前に放射線科へ共有することで撮影条件の調整が可能
2.検査当日受付時
必要情報:現在の腫脹・炎症の有無
理由:炎症があると実影と偽影の判別が難しいため
3.撮影後
必要情報:画像コピーの保管
理由:将来の再注入や溶解酵素投与時の安全マップとして活用

よくある質問(FAQ)
Q1:歯のレントゲン(パノラマ)で頬のヒアルロン酸は写りますか?
A. 通常量(左右各0.5 cc程度)の浅層注入では写りません。ただし頬への深層ボリューム形成を行った場合、灰白色の影として薄く写ることがあります。
Q2:MRIは危険と聞きました。ヒアルロン酸が発熱することは?
A. 現在の医療グレードヒアルロン酸は金属イオンを含まないため発熱はしません。T2強調像で高信号を示すだけで安全性に問題はありません。
Q3:レントゲン前にヒアルロニダーゼで溶かした方が良い?
A. 基本的に不要です。誤診リスクが高い部位(鼻根や頬骨洞付近)かつ大量注入の場合のみ、担当医と相談の上検討しましょう。
画像検査と美容施術を両立する5つの実践アドバイス
1.術前カウンセリングで「レントゲン予定」を必ず申告
2.使用製剤はロット番号まで控え、スマホで撮影しておく
3.深層への大量注入を希望する場合、検査スケジュールを逆算
4.半年以内にCT/PET検査がある場合は注入量を抑える
5.検査後の再注入は医師と画像を共有しながらプランニング
まとめ:ヒアルロン酸注入とレントゲンは両立可能―情報共有が鍵
ヒアルロン酸は基本的にレントゲンに写りにくい安全な充填剤ですが、「高濃度製剤」「深層・大量注入」「撮影時期が近い」の3条件が重なると影響が出ることがあります。美容クリニックと検査機関の「情報の壁」を取り払い、画像診断の精度と美容効果の両方を最大化しましょう。
レントゲン前後の不安は、施術を担当した医師と検査を依頼する医師双方へ遠慮なく相談する姿勢が、あなたの健康と美しさを守る最短ルートです。
ご参考までに下記のメニューをご覧ください。











 ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ
 03-6453-6955
03-6453-6955